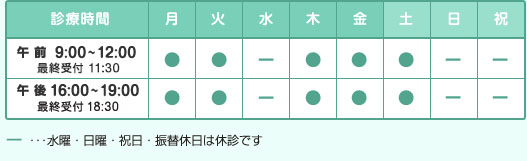リンパ腫の管理(完全寛解という言葉の本当の意味をよく理解して)
リンパ腫とは、リンパ組織のいわゆる腫瘍であって、かつては悪性リンパ腫であるとかリンパ肉腫という名前で呼ばれていたこともある悪性のものである。
リンパ腫は、その発生部位によって、全身のリンパ腺が大きく腫れてくる「多中心型リンパ腫」、皮膚病変として現れてくる「皮膚型リンパ腫」、胃や腸管に出てくる「消化管型リンパ腫」、胸の縦隔という部分の「縦隔型リンパ腫」、腎臓や眼、鼻咽頭、神経に出来る「節外型リンパ腫」などの分類がある。
また、その細胞の分類による病理組織学的分類とか、免疫表現型分類とかいろいろな分類法があって、それぞれ予後(臨床上の将来的見通し)に影響したり、なかなか学問的には難しい点もあるのだが、細かく書き始めると切りがないのでなるべく簡単に行こう。
普通の動物病院で比較的容易に診断出来るリンパ腫は、何と言っても「多中心型リンパ腫」である。 このタイプは犬では最も一般的なリンパ腫であるし誰の目でも非常に判りやすい。 何せ、全身のリンパ節が大きく腫れてくるのだから、臨床症状もはっきりしているし、腫れたリンパ節を細い目の注射針で突いて細胞を採取して顕微鏡で観察すれば、少し慣れれば、普通の黒っぽい小さなリンパ球とは異なる大きな豆大福のような模様のリンパ芽球が主体で、中には細胞分裂像を示すものも結構あったりする特有の組織像が観察されるのだ。
皮膚型リンパ腫や、腸管型リンパ腫などは診断がつくまでにかなりてこずることが多い。 なんだか判らないが治療に反応しない皮膚炎だとか、嘔吐下痢や食欲不振だとかがだらだら続くのは結構要注意なのである。
犬と猫ではリンパ腫の出方も少し違う点がある。 猫にはFeLV(猫白血病ウィルス)という厄介なウィルスが存在して、特に若い猫のリンパ腫はもっぱらこれが原因であることが多いし、猫の場合は犬と違って全身性リンパ節障害よりも内臓機能の異常が出現する割合が高いようである。
リンパ腫の診断方法も基本的には他の腫瘍と同じく細胞診であるとか病理組織診断という腫瘍細胞の検査によって行なわれる。 私の場合、病理学的な知識にはあまり自信がないので、なるべく検査センターの病理の専門の先生に細胞や組織を送って、文書で診断名をはっきりさせてから治療にとりかかるよう心掛けている。
リンパ腫の治療は、基本的には抗癌剤を注射や内服で使用する化学療法という方法を取るのだが、治療に対する反応は発生部位や病理組織学的分類などでさまざまなようである。 しかし、多中心型リンパ腫の場合化学療法にはかなり良好に反応を示す症例が多く、臨床症状が全くなくなって、完全に治ったかとまで思われるくらいになったいわゆる「完全寛解」という状態が、症例によっては半年から9ヶ月、長い例では2年以上も続くことがある。
誤解してはいけないのだが、この「完全寛解」という状態は、決して完全に治癒して再発しないということではない。
抗癌剤の投与によって、リンパの腫瘍細胞の99パーセントが死ぬとするならば、毎週の抗癌剤投与によって毎回99パーセントの腫瘍細胞が死んでいくので、治療を続けることにより、腫瘍細胞の数は限りなくゼロに近づいていくのである。 しかし、決してゼロそのものにはならないのだ。
そして、毎週の投薬で叩き続けていても、いつしか生き残った腫瘍細胞は、その細胞膜上に「P糖蛋白」という細胞に対する毒物を細胞外に排出するポンプのような器官をたくさん備えるという薬剤耐性を獲得して、再び増殖を始めるのである。
リンパの腫瘍細胞が薬剤に対する耐性を獲得すると、これを叩くのはなかなか困難になり、いったんはやっつけるのに成功しても、それによって得られた臨床的に良好な寛解期間は最初の寛解期間よりも著しく短いものに終わることがほとんどである。
そういうわけで、リンパ腫の治療は結局のところ死に至るまでの期間を延長させるというものでしかないのかも知れない。 しかし、多中心型リンパ腫で、症例によっては半年から9ヶ月、長いものでは2年以上という非常に元気でまるで病気ではないかのごとき素晴らしい期間をどのように評価するのかで、この治療の評価は大きく分かれることであろう。
あるクライアントは、数ヶ月くらいの寛解期間であるのならばそれはぬか喜びでしかないので、多額の治療費を費やす価値はないと治療しない方を選択されるし、またあるクライアントは、たとえ数ヶ月でも健康上非常に良い期間が作れるのであれば、それはそれで価値あることとして、その間に動物との思い出を積極的に作るのだと言って治療を選択される。
リンパ腫の治療に対する評価は、クライアントの生きる姿勢というか死生観というものに大きく左右されるように感じているので、治療をするしないのどちらを選択されてもそれはその人の人生哲学の現われであると解釈するようにしている。
結局のところ獣医の私としては、クライアントに対して、自分が診察して収集した臨床上の知見をなるべく正確にお伝えして、それから先はクライアントに判断していただくしかないのである。
なお、抗癌剤療法で気になるのが、薬剤の副作用の問題である。 普通、薬というものは量が少ないと生体に作用を及ぼさず、ある量から望ましい効果が出始めて、量を増やしていくと今度は有害な作用が出てくるものである。 抗癌剤という範疇の薬剤の特徴として、この有効量と中毒量の範囲が狭いということが挙げられる。
従って、抗癌剤の投与量を決定するのに、体重あたりでなく体表面積あたりいくらという計算をすることが多い。 薬剤は身体の細胞の表面に作用するので、身体の長さに対して三乗倍で増加していく体重よりも、実際の体表面積の方が薬剤の投与量の決定により正確な指標となり得るのだ。
抗癌剤に対する動物の反応であるが、多くの犬猫は言われるほどそんなにひどい副作用は出ないものだ。 ただ、中には嘔吐であるとか急な衰弱、下痢、食欲不振などの副作用が現われる個体もあるのであまりにも楽観的に考え過ぎるのも落とし穴に落ちることになりかねない。
副作用に対しては、悲観的にも楽観的にもならず、油断せずという感じで行きたいところである。
リンパ腫に限らず、腫瘍性疾患はその対応に難しいところが多々あるのだが、自分としてはなるべく逃げることをせずに、クライアントがやる気であるのならば積極的に立ち向かいたいと思うのである。