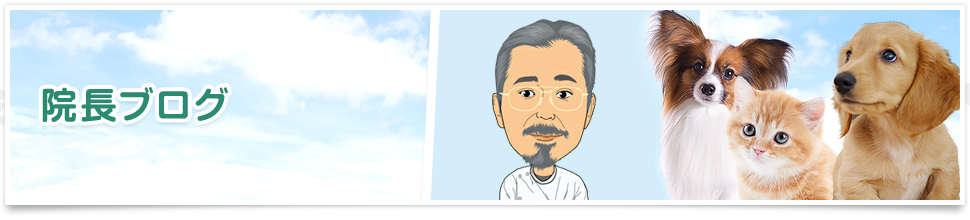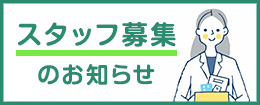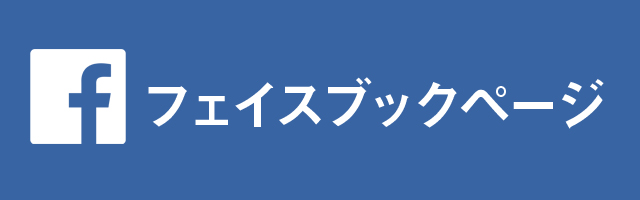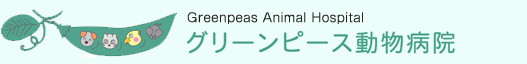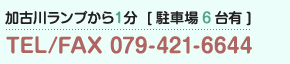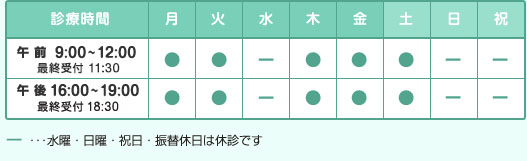皆さんこんにちは
グリーンピース動物病院の更新担当の中西です
さて今回は
~犬の年齢・体況に合わせた食事コントロール~
「何をどれだけ食べさせれば良いのか」は、年齢・体格・去勢有無・活動量・持病の有無で大きく変わります。食事は治療そのものでもあり、逆に合わない食事は疾患のリスクを高めます。本記事では、来院時に私たちが実際に行う評価手順と、ライフステージ別・体況別・疾患別の食事設計を体系化して解説します。
食事設計の前提:評価のフレーム
1) 体重・体型(BCS)と筋肉量(MCS)
2) 活動量と生活環境
3) ライフステージ
4) 既往歴・内科疾患・薬剤
摂取量のベース:必要エネルギーの考え方
1日の基礎計算は**RER(安静時必要エネルギー)**から始めます。
RER = 70 × 体重(kg)^0.75
ここに生活ステージや活動量に応じた係数を掛けて**MER(維持必要エネルギー)**を仮決めします。
-
成犬・室内飼い:1.4〜1.6 × RER
-
活動性が高い成犬:1.6〜2.0 × RER
-
去勢・避妊後の成犬(活動低〜中):1.2〜1.4 × RER
-
体重減量中:0.8〜1.0 × RER(初期設定、進捗で調整)
-
成長期(子犬):
-
体重成長が速い前半:2.0 × RER
-
成長が落ち着く後半:1.6〜1.8 × RER
-
妊娠後半(週数に応じて):1.3〜1.6 × RER
-
授乳期(頭数による):2.0〜3.0 × RER
-
シニア(活動低):1.2〜1.4 × RER
※あくまで出発点。2〜4週間で体重・BCS・MCS・便性状を見て微調整します。
ライフステージ別の栄養設計
A. 成長期(子犬)
-
タンパク質:高消化性・必要量十分(一般に乾物換算で22〜28%目安、品種・製品で差あり)。
-
脂質:エネルギー源。過剰は肥満・成長板への負荷に。
-
Ca/P比:約1.2:1〜1.4:1を維持。特に大型犬の過剰Caは骨関節疾患のリスク。
-
DHA/EPA:脳神経・視覚発達に寄与。
-
給与回数:6か月齢までは1日3回、その後は2回へ。
-
体重増加速度:急激な増量は避け、月次で理想曲線内を推移。
B. 維持期(成犬)
C. シニア(高齢期)
-
MCS維持のため、高消化性で十分な必須アミノ酸を確保。
-
慢性疾患リスクに応じてリン・ナトリウム・脂質の最適化、可溶性・不溶性食物繊維の比率を調整。
-
関節ケア:体重管理が第一。必要に応じてEPA/DHA、グルコサミン・コンドロイチン配合の処方食。
-
腎泌尿器:検査値を見ながらタンパク・リンの段階的コントロール。
D. 妊娠・授乳
体況別の食事コントロール
1) 肥満・過体重
-
目標体重の設定(現在体重の10〜20%減を段階目標)。
-
低エネルギー高たんぱく・適正繊維の減量用療法食を使用。
-
週1回の体重測定、月1回のBCS/MCS評価。
-
間食は1日の総カロリーの10%以内、できればゼロへ。
2) 痩せ(低体重)
3) 胃腸が不安定・便の質に課題
疾患別の要点(簡易ガイド)
詳細は検査値・病期で変わるため、必ず主治医の指示に従ってください。
-
慢性腎臓病(CKD):
早期からリン制限、ナトリウム適正、高消化性タンパクの質重視。脱水回避のためウェットや水分強化。
-
膵炎既往:
低脂肪・高消化性、間食の脂質管理。急な食事変更・暴食回避。
-
肝胆道疾患:
中鎖脂肪酸の活用や高消化性、銅含量の管理が必要なケースも。
-
糖尿病:
一定の炭水化物量と食後血糖の安定、食事とインスリンのタイミング一貫性。
-
食物アレルギー/不耐:
加水分解蛋白または新奇蛋白の療法食で8週間の厳格トライアル。おやつ・薬のカプセル原料にも注意。
-
心疾患:
ナトリウム制限、体重・浮腫・咳のモニタリング、筋量維持。
-
尿路結石:
結石タイプに応じた尿pH・ミネラル管理と水分強化。勝手な食事戻しは再発リスク。
給餌の実務:頻度・食器・水分・おやつ
-
給与回数:子犬3回、成犬2回、疾患やシニアで血糖や消化に配慮が必要なら3回以上へ。
-
食器:浅め・広口で食べやすく、早食いにはスローボウル。
-
水分:複数箇所に新鮮水、ウェットの併用、ぬるま湯で嗜好性を上げる。
-
おやつ管理:総量の10%以内。しつけはフードの取り分けで代用可。
食事の切り替え手順(失敗しない移行)
家庭でのモニタリングチェックリスト(週次)
よくある落とし穴
-
袋の後ろを読まない:カロリー密度は製品ごとに大きく違う。計量スプーン依存は誤差を生みやすい。
-
おやつの積み重ね:小さな一口でも回数で大きなカロリーに。
-
去勢・避妊後の“据え置き量”:代謝が落ちるのに量が同じ→体重増加。
-
短期間で結果を求める:減量は毎週0.5〜1.5%の体重減を目安に、数か月単位で。
ケース別・簡易モデルプラン(例)
実際は体重・検査値・嗜好・生活を聞き取り個別処方します。
-
避妊済み成犬・室内生活・軽運動
MER=1.3×RER。高消化性・中等度脂質の維持食。1日2回、間食はフード取り分け。月1回の体重・BCS確認。
-
活動犬(週4のアジリティ)
MER=1.8×RER。脂質と必須アミノ酸を確保、運動前は軽食または空腹時間を十分とる。水分と電解質の回復を重視。
-
シニア・軽度の腎機能変化
MER=1.2×RER。リン控えめ・高消化性・適正ナトリウム。ウェット併用で水分強化。3か月毎に血液・尿検査。
-
減量プログラム
目標体重設定→0.8〜1.0×RERから開始。高たんぱく・高繊維の減量療法食。週次計測、停滞期は5〜10%追加調整。
受診の目安
-
2週間以上の体重変動(±5%以上)
-
慢性的な軟便・嘔吐・食欲低下
-
被毛の急な艶低下・皮膚トラブル
-
急な多飲多尿、運動不耐性、咳や呼吸の変化
-
去勢・避妊後の食欲増進と体重増加が止まらない
まとめ
食事コントロールは「フードの銘柄選び」だけではありません。RER→MERで量を仮決めし、BCS/MCS・活動量・便や被毛の状態で2〜4週間ごとに調整するのが実務の核心です。年齢・体況・疾患に応じた目的別の処方食を使い分け、水分・給与回数・おやつ・運動を含めた総合設計で、長期的な健康とQOLを守りましょう。気になる変化があれば早めにご相談ください。